ドイツで良い議論ってどんな議論展開だろう?
ぼくのドイツ語教師は控えめに言って「議論がめちゃくちゃうまい」とぼくは思う?
目次
ちなみにドイツ語教師はどんな人?
ギリシア系ドイツ人の女性。かりにAとしておこう。
「ギリシア系」とは両親が純粋なギリシア人で、Aはドイツで生まれ育ったドイツ人であるということ。
余談 ~系ドイツ人の話
余談になるが、ドイツにはギリシア系2世、3世はけっこー多い。
戦後のドイツは労働力が圧倒的に足りなかったために、ギリシャ人とアルメニア人に居住権をばら撒いて、労働者を増やしたのだとのこと。
また、余談になるが、ドイツでは、~系ドイツ人はめずらしくない。
ぼくの周りにも、ベトナム系ドイツ人、トルコ系ドイツ人、イラン系ドイツ人・・などなど、よく見かける。日系ドイツ人も2人知っている。
だから、ドイツでは、見かけだけで「~人」と判断するのはナンセンスである。
で、話は戻るけど
で、話を戻すと、ぼくのドイツ語教師Aはギリシア系だ。
Aの授業は他の生徒から、非常に評判が良い。ぼくもそう思う。
不憫なことに、他の教師と比べられて「~の授業ってつまんないよね。Aの授業はおもしろいけど!」という生徒も多い(サンプル数は10人くらい)
これは、ぼくの主観になるが、きっとAは「外国人には伝えるうまい方法」を感覚的に知っているのだろうと思う。
Aはギリシア人の家庭で育って、ドイツ社会で育っている。ということは、2つの社会環境で育ったと言える。
たぶん、そういうところから出てくるAのコミュニケーションスタイルや教え方が外国人であるぼくたちにウケるのだと思う。
で、どんな議論スタイル?
Aは授業の中で「議論」が一番すきなのだそうだ。と、本人が言っていた。
授業での議論とは、Aがテーマを生徒たちに与えて議論をさせて、ときどきAが議論を脱線しないように修正するスタイルのこと。
で、Aが主催する議論は「うまい」と言っても、たぶんこれを読んでる人にはまったく伝わらないだろう。
なので、まずはぼくがAの議論で感じることを書いてみる。
Aの議論でぼくが感じること
別の言葉で言うと「ぼくにとっての議論が上手である」ということの基準・定義とも言える。
- 自分が発言した「ふつう」ってなんだろう?と考えるきっかけになる。
- 自分の意見を極論化させると、自分でも考えてもなかった帰結になってしまう。と気づく
- 話が脱線して論理のつながりが不明になることが滅多にない。
- ぼくのドイツ語力不足で、単語理解不足から、論理が追えなくなることはある。
- あ、なんか楽しかったな!自分の意見を言ったし、他の生徒の価値観もしれたし!という気分になる。
- 「論破された!クソッ」という気分には決してならない。ネガティブな気持ちがまったく沸き起こってこない。
Aが主催する議論タイプはどんな感じだろうか?
※日本語でいい感じに書いているけれど、すべてドイツ語で会話している。
もうちょっと、具体的に伝えたいので、例をひとつ上げてみる。テーマは「麻薬は合法販売されるべきか?」
Aの議論のうまさを説明できそうなところ(特徴量)に、赤強調をしてみた。ぜひ、そういうところに注意しながら読んでみてほしい。
生徒1 「そんなのふつうはダメに決まっている!」
A「どうして?ふつうって何?」
生徒1 「ええと。。。それは私の国ではふつうだから(生徒1はイスラム系国家出身で麻薬は違法)」
A 「OK。たしかにそうね。まずは、ドイツの例で考えてみましょう。ドイツでも麻薬は違法ね。これはいいことかしら?」
大半の生徒 「そうだね」
A 「でも、私はタバコとアルコールは麻薬よりも依存性が高いと読んだことがあるわ。麻薬よりも依存性が高いものが許可されているのは変じゃない?麻薬が禁止なら、タバコとアルコールは禁止されるべきじゃないかしら?」
生徒2(ロシア系)「それは困る!アルコールはなしでどうやってパーティしろっていうのよ!アルコールなしのパーティじゃ、彼氏も見つけられない」
A 「それなら、アルコールは販売OKと。と、いうことなら、麻薬も販売してOKじゃないからしら。つまり、スーパーで麻薬を販売してもOKってことね。どう思う?」
生徒3「えー。それは変だよ。なんだか、危ない感じがする。」
A「どうして?どういうところに危なさを感じるの?」
生徒3「うーん。麻薬ってネガティブなイメージと結びついているよ。ほら、街のあのあたりによく麻薬やってる人と売人がいるじゃん(注:住んでる街には有名な治安が悪い地区がある)」
A「そうね、たしかに麻薬とネガティブなイメージはつながっているわね。じゃあ、オランダの例を考えてみましょう。オランダでは制限付きで麻薬は合法よ。麻薬を合法化することのメリットはあるかしら?」
….以下略
どうしてAの議論はうまいのか?
赤線を引いたところから、Aの「議論のうまさ」を抽象化してみる。
条件なし「ふつう」の存在を許さない。
誰にとって、どの条件で、どうして、「ふつう」なのか?ということを追求する。
もしA(命題)なら、B(命題)もOKになるんじゃない?
「麻薬が禁止なら、タバコとアルコールは禁止されるべきじゃないかしら?」の発言から。
一見すると、社会の常識から外れること「タバコとアルコールの販売禁止」も、「AならばBじゃない?」の論理構造で質問を投げかけてくる。
だいたいの場合は、回答は「いやいや、それは拡大解釈だよ!社会には難しいところがあるよ」になるだろう。
でも、そういうときAは「どうして?どういうところに難しさがあるの?」と「どうして」を繰り返してくる。
注意しておきたいのは、Aには「はいはい!論破!ロンパー!!」みたいな態度がまったくないところ。
あくまで、「どうして?」「なぜ?」から、議論テーマの背後にある色んな社会問題や事象を明らかにしていこうという姿勢がある。
~すること(命題A)のメリットは何がある?
「麻薬を合法化することのメリットはあるかしら?」の発言が対応。
だいたいのできごとには、メリットとデメリットがあるものだ。
一面だけを見ても、大切なことにはたどりつけない。
そこで、「麻薬を合法化すること」の「メリット」にも注目してみるというわけだ。
実際のところ、Aは授業でも「~ということには2面性があるわね。メリットは~。デメリットは~。」のような話し方が多い(他の教師との比較してみても、明らかに多い)
つまり、どういうこと?
ぼくはAの議論スタイルを「良い議論だな」と感じる。Aの議論スタイルを分解して考えてみると、次のような要素があった。
- 条件付なしの「常識」を追求する。どうして?なぜ?誰にとって?の質問で追求
- 「あなたの言っていることが本当なら、~ということも起きるんじゃない?」と拡大解釈の質問を投げかける
- 「(テーマ)のメリット(またはデメリット)は何がある?」と質問を投げかける
そして、これは一番に大切なことだけど、Aは「対話を楽しんでいる」
「ロンパー!ロンパー!ねぇ、どんな気持ち~?」のような姿勢は微塵もない。
(参考動画)ねぇ、どんな気持ち~?
悪意のある書き方をしてしまったが、ぼくは「論破野郎」が大嫌いだ。
どれくらい嫌いかと言うと「抜刀術で口部分を切って、しゃべれない様にしてやりたいくらい嫌い」だ。
おそらく、ぼく自身にも「論破野郎」の一面がどこかあるのだろう。
人間、自分のもつ嫌な面を持った他人をみると苛立ってしまう。こういうのを心理学ではシャドウ(投影)というらしい。参考
ぼくの中にも潜む論破野郎を助長しないように生きていきたいものだ。
うまい議論?の参考までに
「まこなり社長」というYoutuberがいる。
なかなかサイコパス感を出している経営者(褒め言葉)で、ぼくは彼の動画を見るのが好き。
で、「まこなり社長」の動画に「うまい議論をしていくために必要なこと」というテーマがあった。
このビデオをまとめた記事もあるので、ぜひ読んでみてほしい。
彼の言うことを一言でまとめると「相手の意見と逆のポジションを考えてみて、質問をなげかけてみる」ということである。
考えみればみるほど、これを具体化したのがAの議論スタイルに感じる。
まこなり社長は冒頭でソクラテスの話をあげているが、ソクラテスはギリシア人。
Aもギリシア人。関係あるんだろうか?。。。とそんなことをふと思った(そんなわけない)
ってか、なんでこんな記事かいたの?
ぼくはAの議論スタイルが上手と感じていた。
ある日、ぼくは「議論の上手ってなんだろう?」、「どうしてAの議論はうまいんだろう?ぼくは真似できるだろうか?」と思いはじめた。
分析していくうちに、「これって文化に関係なく、普遍的な考え方なんじゃないか?」と思いはじめた。
で、まこなり社長動画をみて、「日本人でも可能なはずだ」と確信を得た。
なので、ぼくがうまく議論の方法を実践してみるために、あえて文面に書き起こしてみた。
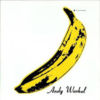

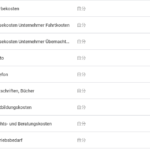

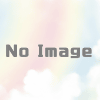

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません